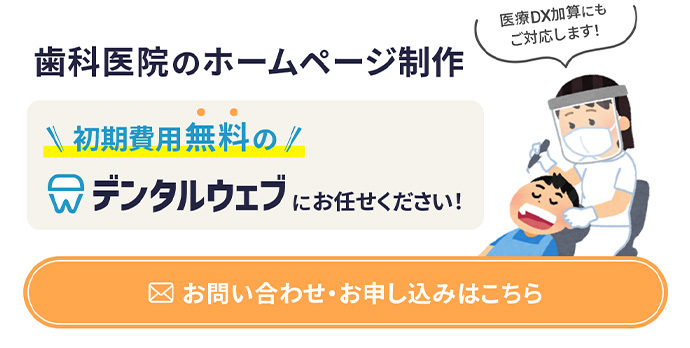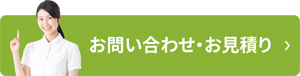歯科コラム
歯科医院ホームページは大丈夫?医療広告ガイドラインに違反しやすいNG表現と対策まとめ【最新2025年対応版】

現在、日本全国にある歯科医院の数はおよそ7万件。
実はこれは、全国のコンビニエンスストアの数よりも多いと言われています。歯科は、まさに「選ばれる時代」に突入しているといっても過言ではないでしょう。
そのため、「この歯医者に行きたい」と思ってもらうためには、ホームページや広告が欠かせません。とくに最近では、歯科衛生士や歯科助手などの採用活動においても歯科ホームページが大きな役割を果たすようになっています。
しかし、ここで見落とされがちなのが「医療広告ガイドライン」の存在です。
歯科医院を含む医療機関の広告には、法律によって厳しいルールが定められており、それに違反した場合には懲役6ヶ月または30万円以下の罰金が科される可能性もあるのです。
今回は、実際に多くの歯科医院で使われがちな表現の中から、特に注意が必要な3つのNG広告、
-
虚偽広告
-
比較優良広告
-
誇大広告
に絞って、具体例とともにわかりやすくご紹介していきます。
なお、「医療広告ガイドラインにそったホームページ制作」についての詳細や、加算算定に対応した設計についても後ほど触れていきます。
【歯科医院のホームページ制作なら「デンタルウェブ」】
初期制作費0円! 日本全国オンラインで迅速に対応! こだわりのサイト制作にも対応可能!
デンタルウェブでは、初期制作費無料で、歯科医院ホームページを制作いたします。
デンタルウェブのおすすめポイント
- 初期費用を抑えて歯科ホームページを制作可能
- 集患のためのSEOを意識した構築を徹底
- 実績十分のWEB制作スタッフ
他にも、費用にこだわらず徹底してこだわった歯科医院・歯科医師会・歯科技工所などのサイトを作りたい場合や、矯正歯科、インプラントなどの歯科LP制作、広告運用のご相談にも対応します。
今すぐ詳細を知りたい方は、以下よりお問い合わせください。
目次
そもそもホームページは「広告」にあたるのか?

医療法改正以前は、医療機関のホームページは原則として広告規制の対象とされていませんでした。
ところが、2018年に「改正医療法」が施行され、医療機関のウェブサイトも他の広告媒体と同様に規制対象となりました。
つまり、テレビCMや折込チラシと同じように、ホームページに掲載する内容にも法律に沿った制限が設けられるようになったのです。
この改正によって、歯科医院のホームページでも「どんな表現が許されるか」「何を書いてはいけないか」という判断が必要になりました。
たとえば、
-
科学的根拠のない治療効果の断言
-
他院と比較して優れていると見せかける表現
-
芸能人や著名人の利用を強調するような紹介
などが該当します。
中でも問題となりやすいのが、医院側には悪意がなくても、結果的に「誤認を与えてしまう」表現です。
歯科ホームページは「信頼の入り口」です。
仮に内容に嘘がなくても、事実を強調しすぎるとNGになる可能性があります。
このように、医療広告ガイドラインに沿った表現を心がけることは、法令遵守のためだけでなく、患者様との信頼関係を築く第一歩でもあるのです。
虚偽広告とは?禁止される表現・ありがちな具体例

医療広告ガイドラインの中で、最も明確に禁止されているのが「虚偽広告」です。
虚偽広告とは、事実と異なる情報や、誤解を招く表現によって患者に誤認を与える内容を指します。
実際には、一見して「そんなことはしていない」と思われる箇所も少なくないと思います。
しかし、悪意はなくても、うっかり使ってしまいがちな表現が意外と多いため、より注意が必要なのです。
以下に具体例を挙げて見ていきましょう。
虚偽広告のNG例
「絶対安全です/必ず成功します」
医療において「絶対」は存在しません。たとえ成功率が高い治療であっても、個々の患者様の状態によって結果が異なる可能性があるため、「必ず」や「100%」という表現はNGです。
(ちなみに、某医療ドラマでおなじみの「わたし、失敗しないので」というセリフも、現実の医療広告では使用するだけで違反と判断される可能性があります。)
「実際よりも加工された写真を掲載」
ホワイトニングや矯正治療などのビフォーアフター画像を過剰に美化して掲載することも、事実と異なる印象を与えるとして問題になります。
特に、歯の白さを画像編集ソフトで「美白加工」してしまうケースは注意が必要です。
実際の治療効果を過度に演出してしまうと、虚偽と見なされる恐れがあります。
「1日で全ての虫歯治療が終了します」
一見便利に思えるこの表現も、治療後の経過観察や定期検診が必要になるケースがあることを考えると、実態と食い違う可能性があります。
そのため、「一日で終わる」と断言することは避けるべきです。
患者様との信頼を守るために
虚偽広告は、単に法律に触れるだけでなく、患者様の信頼を損なう大きなリスクにつながります。
少しでも誤解を与える表現がないかどうかを、第三者の目でチェックする姿勢が大切です。
また、ホームページ制作会社やライターに依頼する際も、医療広告の知識があるかどうかを確認しておくと安心です。
比較優良広告とは

「うちは県内で一番の設備を誇っています」「有名人も通う人気の歯科医院」
このようなキャッチコピーを、どこかで見かけたことがあるかもしれません。
ですが、こうした表現こそが「比較優良広告」にあたる可能性の高いNG表現です。
比較優良広告とは、他の病院や診療所と比較して自院の方が優良であることを強調する内容の広告を指します。
たとえそれが事実であっても、患者様に誤解を与えたり、過剰な期待を抱かせたりする恐れがあるため、医療広告ガイドラインでは厳しく制限されています。
比較優良広告のNG例
「当院は県内一の医師数を誇ります/日本有数の実績を有する歯科医院です」
このような「最上級表現」は、たとえ客観的なデータに基づいていたとしてもNGです。「日本一」「最高」なども同様です。
医療の世界では、「No.1」や「最大級」「最多」といった言葉は、事実かどうかよりも「受け取られ方」が問題になることが多くあります。
「有名モデルも通院中/○○誌で紹介されました」
著名人の名前や、雑誌・テレビ番組などの紹介実績を強調する表現も注意が必要です。
一見すると信頼感を高めているように思えますが、他院より優れていると印象づけるような効果があるため、広告表現としては不適切とされています。
実際に掲載されていたとしても、「○○に紹介されました」という形で宣伝に使うのは避けるべきです。
「実績」の伝え方
実績や症例数などをアピールしたい場合は、事実だけを淡々と伝える工夫が必要です。
たとえば、「開院から〇年が経ちました」、「年間○○件の診療実績があります(※2025年実績)」など、数字と出典を明記し、感情的な表現を避けることで、患者様に正確な情報を届けることができます。
比較優良広告は、患者様に「この医院なら安心できる」と思ってもらいたいがあまり、つい使ってしまいがちな表現です。
ですが、他院を引き合いに出すのではなく、「自院の特色やこだわりを丁寧に伝える」ことが、結果的に選ばれる理由になります。
誇大広告とは?「言いすぎ」に注意したい表現

虚偽ではないけれど、ちょっと大げさ。そんな表現が「誇大広告」にあたることがあります。
実際には、事実を述べているつもりでも、それが受け手に誤解を与えたり、不当に期待を持たせたりするようであれば、ガイドライン違反と見なされる可能性があるのです。
誇大広告とは、必ずしも虚偽ではないが、事実を過度に誇張して表現していたり、実態を正確に反映していない形で表現してしまっている広告を指します。
医療の現場では特に、患者様の命や健康に直結するため、わずかな誇張でも「誤認リスク」とされる厳しい基準が設けられています。
誇大広告のNG例
「比較的安全な手術です」
「比較的」とは、何と比べてなのか、その比較対象が明示されていないため、この表現は誇大とされることがあります。
たとえ手術のリスクが低かったとしても、「安全」と断言することには慎重さが求められます。
患者様によって状態やリスクが異なるため、一律の安全性は保証できないからです。
「○○手術は効果が高く、おすすめです」
この表現は、一見すると患者様への親切なアドバイスのように見えます。
しかし、科学的根拠が不明確な場合や、医師の主観による表現である場合には、誇大広告と判断される可能性があります。
特に「おすすめ」という言葉は、患者に過度な期待を抱かせやすく、医療情報としての中立性が損なわれやすいため、使用には十分な注意が必要です。
信頼される情報発信のために
誇大広告を避けるには、以下の点を意識しましょう。
-
客観的事実を元に表現する(例:「〇〇学会のガイドラインに基づいて実施しています」)
-
「〜です」「〜できます」と言い切らず、「〜することもあります」など、やわらかい表現を使う
-
推測・希望的観測に基づいた表現は避ける
誇大広告を避けることは、法律のためだけでなく、患者様との「正直なコミュニケーション」を守る姿勢にもつながります。
医療広告ガイドラインに沿った歯科ホームページ制作

これまでご紹介してきた「虚偽広告」「比較優良広告」「誇大広告」は、いずれもうっかり使ってしまいがちな表現ばかりでした。
では、実際に歯科医院のホームページ制作を行うにあたっては、どのようにすれば医療広告ガイドラインにきちんと対応できるのでしょうか。
今のホームページを「チェック」
すでにホームページをお持ちの歯科医院さまの場合、まず現在の内容を一度見直してみることが大切です。
特に以下のようなポイントを確認してみましょう。
-
「必ず治ります」など、断定的な表現はないか
-
他院との比較を示すような言い回しが含まれていないか
-
芸能人や雑誌などの実績を強調しすぎていないか
もし少しでも心当たりがある場合は、早めに修正を検討しましょう。
医療広告ガイドラインに抵触した場合、意図がなかったとしても行政指導や罰則の対象になる可能性があります。
これから新しくホームページを作る場合
これからホームページを新しく制作したいとお考えの方は、制作段階からガイドラインを意識した設計を心がけることが重要です。
たとえば、
-
診療内容は中立的に、根拠に基づいた言葉で説明する
-
治療のメリットと同時にデメリットも正直に記載する
-
写真や症例は、実際の治療結果を過剰に演出しない
これらを意識するだけでも、安心して見られるホームページになります。
結果的に、患者様の信頼獲得にもつながります。
デンタルウェブでは、医療広告ガイドラインに沿った形で制作を行っておりますので、安心してお任せください。
医療DX推進体制整備加算への対応も視野に
最近では、「医療DX推進体制整備加算」という診療報酬項目が新設されるなど、ホームページ制作に関する役割がますます広がっています。
この加算では、オンライン資格確認の対応状況や、情報通信技術(ICT)を活用した診療体制の整備などが求められており、医院のホームページにもその情報を適切に掲載することが条件の一つとされています。
そのため、ホームページ制作会社を選ぶ際には、医療業界の最新制度に対応しているかどうかも重要な判断材料となるでしょう。
デンタルウェブではそうした最新の医療業界の事情にまで対応、あらかじめ用意している診療コンテンツを選択するだけですので、打ち合わせや原稿の準備・規定のチェックなど、お忙しい先生方の手間を省くことができます。
関連記事:「医療DX推進体制整備加算におけるホームページ制作と対応について解説/歯科・医科・調剤」
忙しい院長先生のためのサポート
「日々の診療で手が回らない」「何をどう書けばいいのか分からない」
そんな先生方には、あらかじめ医療広告ガイドラインに配慮したテンプレートや文章構成が整った制作サービスを活用するのも一つの手です。
たとえば、当社デンタルウェブでは、診療科目別の構成案や原稿ひな形を多数ご用意しており、打ち合わせや原稿チェックの負担を大幅に軽減できます。
先生方が本来の業務に集中できるよう、「法令遵守」と「集患効果」の両立を意識した設計をお手伝いしています。
歯科医院のホームページ見直しをご検討の医院さまはお気軽にご相談ください。